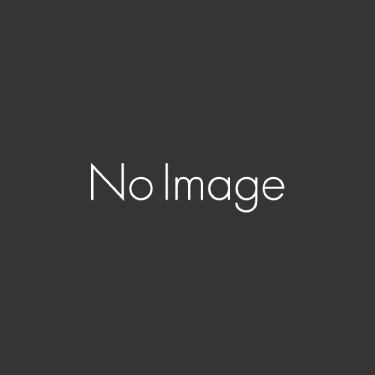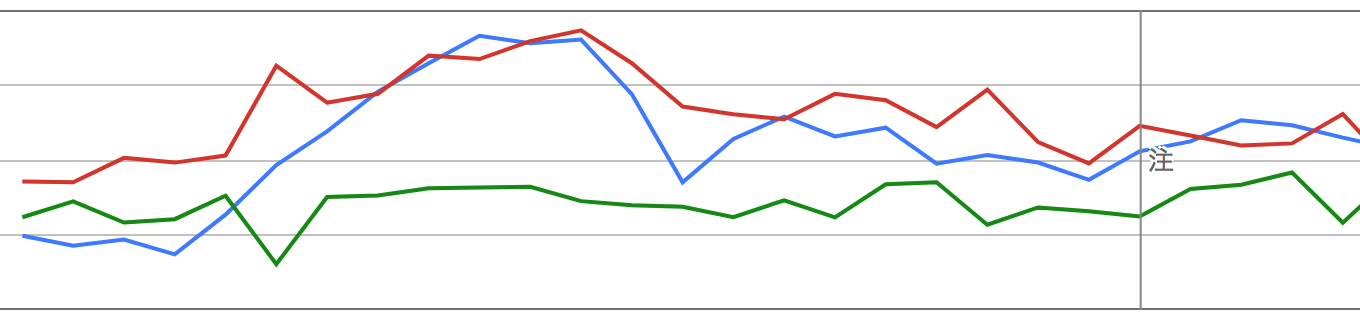ホームページは作って終わりのサイトがほとんど。
たくさんのホームページを見てきて断言できます。
ホームページを例えの一つとして、小さなスーパーの経営をしているとします。
お客様の動線に沿って、商品を陳列し、売上を上げたいのであれば、随時、場所を変えたり、見せ方を変えたりしていきます。
お店の奥に、人気の商品を置いて、回遊性を高めようなど。
でも、不思議とホームページは作って終わりです。
逆を言えば、ちょっとした工夫を積み重ねれば、売上が上がり、他社に勝てるということです。
あと、数万回言おうと思います。
変な話、工夫するのが当たり前だと思っていたのですが、世の中はそうでないみたいで…。
ブログで言えば、自分を追い込むかのように、更新回数だけ意識して、あとはどうにかなるというスタンスが多い。
苦しいのが好きな人にはいいですが…。
私の今後の課題として、ウェブサイトは作成して、はじめて、スタートライン、終わりではないということを啓蒙活動していこうと思います。